誰しも子どもが生まれたら『いい親でありたい』と望むのは当然のこと。しかし『いい親』を目指すことで、周りと比較して自分が苦しくなってしまうことがあります。
HSPの自分だからこそ、余計考え過ぎて、自分を追い込み辛くなってしまいます。
子育てで『しないこと』を決めれば、親自身が心身ともに楽になる。『しない』子育てで、ママもパパも子どもも幸せになれる。
『いい親よりも』大切なことを書いていきます。
・子育てが楽になる!たった6つのしないこと
・「しない」子育てで、ママも子どもも幸せに!
参考文献:いい親よりも大切なこと ~子どものために“しなくていいこと”こんなにあった!
子育てが楽になる!たった6つのしないこと

子どもにすべてを教えない
子ども自身に考えさせる
子どもは、初めからおもちゃの使い方を知りません。私自身も最初から「こうやるんだよ」と、誘導してしまっていました。
しかし、子どもは遊び方を知らないので、親の役割は、やり方を誘導してあげることです。子ども自身で触ったり、考えさせて、遊び方を自発的に考えるクセをつけさせてあげると良いです。親はそのキッカケを与える補助的に役割が理想です。
子ども自身がおもちゃを触ったり・たたいたり・舐めたり・動かしてみて、その使い方を自ら発見するのです。
ここ最近よく言われるような『非認知能力』や『自走力』が芽生え、自ら考えて行動できる力を養います。
親は、そんな子どもを見守る勇気が必要です。
- 子ども自身で遊び方を発見させる
- 親は補助的な役割で、見守る
「してあげなきゃ」リストをつくらない
『いい親』を目指さない
多くの人が、「子どものために、もっといい親でいなきゃ」という呪縛にかかって苦しんでいるということです。
P24から抜粋
親なら誰しも「こうあってほしい」という理想像が存在します。
- 自立している
- 責任感がある
- リーダータイプ
- 勉強が得意
- スポーツ万能
- 芸術的センスがある
- 社交的
- 周りに親切
- etc・・・
こうした願望を叶えてあげたいと思った結果、『してあげなきゃ』リストを自分に課してしまい、苦しくなってしまいます。
理想を追い求め過ぎてしまう結果、それに応えることができなくて、逆にストレスになってしまいます。周りと比較していたら、キリがありません。
そもそも『いい親』の定義は何でしょうか?人の数だけ、正解があります。
無理をして頑張りすぎて、自分自身がイライラしていたなら、子どもに優しく接することができるのでしょうか?
子どもは少しずつ、できることも増えていきます。等身大の自分を受け入れたなら、『いい親』を目指さなくても大丈夫です。
- 『いい親』を目指さない
- 等身大の自分を受け入れる
生活リズムに縛られない

完璧を求め過ぎない
子どもの生活リズムを完璧にこなそうとしてしまうと、親自身もそれが達成できなかった時に、ストレスがたまります。
- 一日三食、時間通り
- お風呂は毎日入れる
- 離乳食は月齢通り手作りで
- 決まった時間に寝かすetc・・・
これらのことを完璧にこなすことは不可能です。その時その時でベストな選択をすればいいのです。
食事に関していえば、一週間を通じて体重が落ちていないかなどを目安にすればいいのです。夜にお風呂に入れなかったら、翌日でもかまいません。
離乳食は必ず手作りにする必要がありますか?共働きで忙しいのならレトルトや冷凍食品に頼ってもいいのではないでしょうか。
子どもができなかったことに苛立つ必要はありません。
大人の都合に合わせない
子どもは大人のように、規則正しく時間通りに生活できるわけではありません。子どもには自分のペースがあり『今していることを大切にしています。』
保育園で子どもが塗り絵に夢中になっていたら、強制的に終了させては可哀そうです。ただどうしても、帰らなければいけない場合など中断しなければいけないこともあります。
それなら
- 「もっと塗り絵やりたかったよね」と共感する
- 「今やっているものが終わったら帰ろうね」と期限を設ける
- 「帰ったら楽しみにしてた、~やろう」と促すなどが
子どもに対する優しさだと思います。子どものやりたいことを尊重して寄り添ってあげることが、子どもの自己肯定感を高めることにもつながります。
- 完璧を目指さない
- 子どができなかったことに苛立たず受け入れる
- 子どものペースを大切にする
- 温かく見守る
いつも笑顔じゃなくていい

愛想笑いが増えていませんか?
大人になるにつれて、私たちは笑顔をコントロールするようになります。
『空気を読む』という言葉があるように、その場面に合わせて、愛想笑いや作り笑顔をしたことがある人は多いのではないでしょうか。
それは決して悪いことではないのですが、そればかりになってしまうと自分が辛くなっていきます。時には我慢せず喜怒哀楽を表現してもいいのだと思います。
笑顔と元気だけが全てではない
毎日、笑顔と元気に過ごせたら、それは素晴らしいことです。しかし、それは不可能です。子どもだって、体調が悪ければ元気がないし、なんとなくやる気が出なくてボーっとする日だってあります。
友達とケンカをして、ずっと拗ねていることだってあります。
子どもの中に芽生えた感情を認めてあげることが、安心感につながります。
辛く悲しい時は泣いていいし、怒ったり、楽しんだり、喜んだり、喜怒哀楽には意味があります。子どもにはそのひとつひとつの感情を大切にしてほしい。親にはその子どもの気持ちに共感して、寄り添ってあげればいいと思います。
そのあと、自然に出る笑顔が素晴らしいものでは、ないでしょうか。
- 時には喜怒哀楽を我慢しない
- 笑顔と元気だけが全てではない
- 子どもの気持ちに共感して寄り添う
子どもを100%愛そうとしなくていい
愛の形は様々
子どもが自分の思い通りに育っていないのは、100%愛していないからだと、思い詰めていませんか?
そもそも100%の定義が曖昧だし、人の数だけ愛し方もあります。自分が思っていることと、周りからの見えかたも違います。
「自分は親として完璧ではない」と思い悩む必要もありません。
日々を一緒に過ごすことだけでも価値があります。積み重ねた時間が後になって、信頼や愛情になります。
子どもは愛情を貯めることができません。なぜなら愛情を受け取る器が小さいのです。だからこそ、子どもと触れ合う時間を大切にしてほしい。その方法は、人それぞれのやり方でかまわないのです。
- 絵本を読む
- ご飯を作ってあげる
- 一緒に遊ぶ
- 一緒にお風呂に入る
- 添い寝する
- ハグなどスキンシップをするetc・・・
一日数分だけでもかまわないのです。片手間ではなく、子どもとふたりだけの時間を作ると愛情が深まります。
- 人の数だけ愛し方がある
- 完璧な親になろうとしなくてもいい
- 愛情貯金はできないから、日々少しだけでもいいので、子どもと向き合う時間をつくる
子育てに軸はいらない
軸は変わってもいい
自分の軸が定まっている人はカッコ良く見えたりします。自分の考えに一貫性がないことに、時折不安を覚えることもありますが、それはそれでいいのです。
幼少期はスイミングを習わすのがいいのか、体操がいいのかで悩みます。それぞれに正解はありませんが、軸が変わるからこそ、その時に周りからのよいアドバイス受け入れる柔軟さがあるとも言えます。
習い事を続けていても途中で合わないなど、違和感が生じてくるのは当たり前なので、絶対に~を続けないといけないと、頑固に軸を変えないのは無意味です。
子育ての常識も時代とともに変わっていきます。
- 日光浴をさせる
- 抱っこはし過ぎない
- 予防接種後は入浴させない
- おむつは2歳まで、授乳は1歳までetc・・・
これらの過去の常識は、現在変わってきています。
様々な価値観がある
夫婦でも子育てに考え方の違いがあります。それは、どちらかが正しいというわけではありません。様々な価値観があるから、答えはひとつではないと、子どもにも多様性・柔軟性の考えを伝えることができます。
- 軸が変わるからこそ、柔軟性や多様性を受け入れ、新しい価値観を得られる
「しない」子育てで、ママも子どもも幸せに!
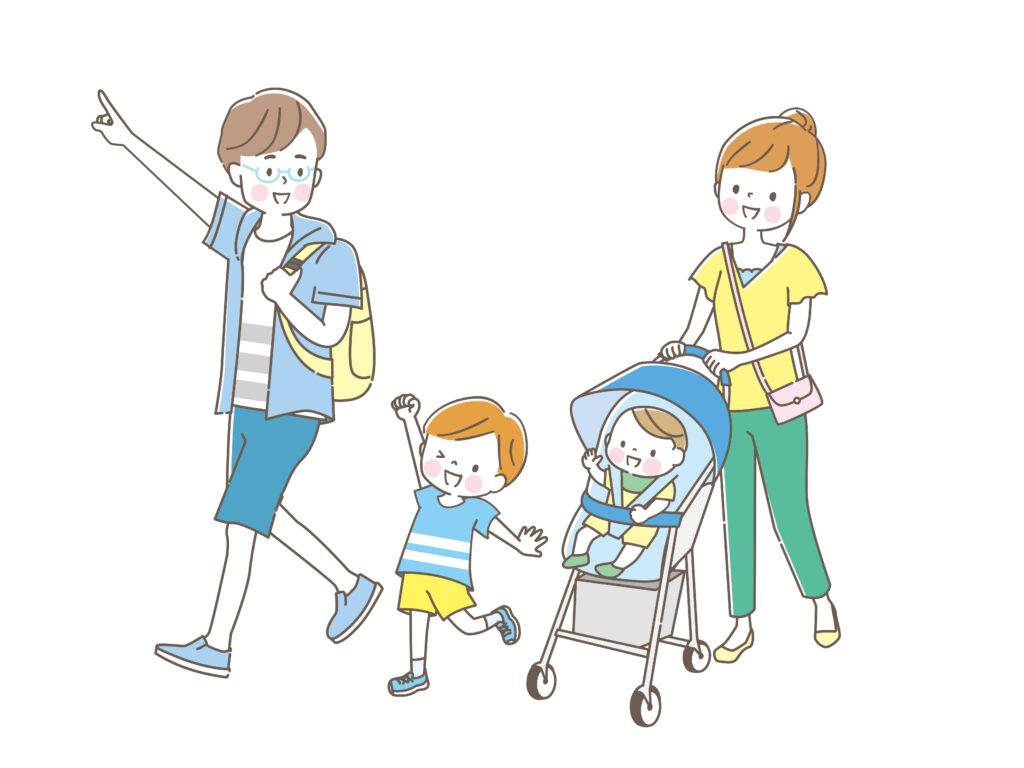
子どものためのママ友はいらない
自分の気持ちを犠牲にして、周りに合わせなくてもいい
子どもは大人の思っているより、たくましく成長していきます。
子どもが社交的に育ってほしいと思い、保育園や幼稚園でのママ友パパ友付き合いを無理してませんか?本来は人見知りで、居心地が悪いのに愛想笑いしていませんか?
うわべだけの付き合いなら、自分が疲れてしまうだけなので、必要ありません。子どもは、年齢があがるにつれ環境に適応していきます。
コミュニティは身の回りにたくさんある
私自身、公園デビューは気が重く感じました。でも、それだけがコミュニティの全てではありません。
自分の家族や親せき・友達・行きつけのお店の店員さん・習い事の知り合いなど、年齢も性別もバラバラな人との付き合いで、子どもの社会性が育まれます。動物との触れ合いでもいいと思います。
自分の気が進まないコミュニティに無理して入り込まなくても、身近なコミュニティの関係性を深めていくことに注力したほうが好ましいです。
- 自分が思っている以上に子どもは環境に適応していく
- 馴染めないコミュニティで自分自身を消耗させない
自分の”好き”を見失わない
親でもあるが、たった一人の自分
初めての子育ては不安でいっぱいです。ワンオペの状態が長く続けば続くほど、何が正解かわからなくなります。SNSでは情報が溢れ、自分は孤立していると思い、ますます不安になります。周りの人に助言を求めても、人によって意見はバラバラ。
そんな時は、一度立ち止まって、ゆっくり考え時間が必要です。答えはいつだって自分の中にあり、自分で答えを出せば苦しくないのです。
周囲に流されず、自分だけの正解を導けばいいのです。
忘れかけていた自分の好きを取り戻す
子どもには、自由で自分に正直に生きて欲しいと願います。一方、親はそのように生きているでしょうか?
子どもにも、好きな遊び・音楽・動物・色など、人それぞれです。親だって、子どもと好きなものやことが違うのは当然です。
理由もなくなんとなく、好きだという感情を親も大切にして欲しい。好きなものに囲まれている生活は、なんとなくテンションがあがり、元気になります。
それぞれの好きがあっていい
親だって子どもの頃は好きなものがたくさんあったはずです。成長する過程で、いつの間にか忘れてしまっています。
子どもにも親の好きなことに夢中になっている姿を見せることも重要です。その背中を見て、家族の中で、尊重し合える関係を築くことができます。
- 立ち止まって考え、自分だけの正解を見つける
- 自分の好きという感情を大切にする
- それぞれ好きなものを尊重する
「凸凹論」という考え方

凸凹論とは?
「自分自身の強みや弱みを含めた特性に気づき、受容することで、結果的に、他社のもつ特性をも受容できるマインドがつくられていくこと」
P159引用
人にはそれぞれ強みと弱みがあります。大人になるにつれて、できないことは『恥ずかしいこと』と認識してしまいます。
しかし、強みと弱みは表裏一体です。HSPは繊細で感情の揺れが多くてネガティブなことに敏感だけれども、反面、小さな喜びを見つけることができたり、共感できる感受性の豊かさを持ち合わせています。
それが個性です。苦手なことがあれば、周囲にお願いして助けてもらえばいいのです。自分の弱さを認めることができたら、他者の弱みも受け入れることができるようになります。
人はみな凸凹であるからこそ、子育てにおいても、「自分ができたから子どももできるはず」と理想を押し付けてしまうこともなくなるはずです。
- 自分の強みも弱みも個性であると理解すれば、他者のことも寛容に受け入れることができる
まとめ
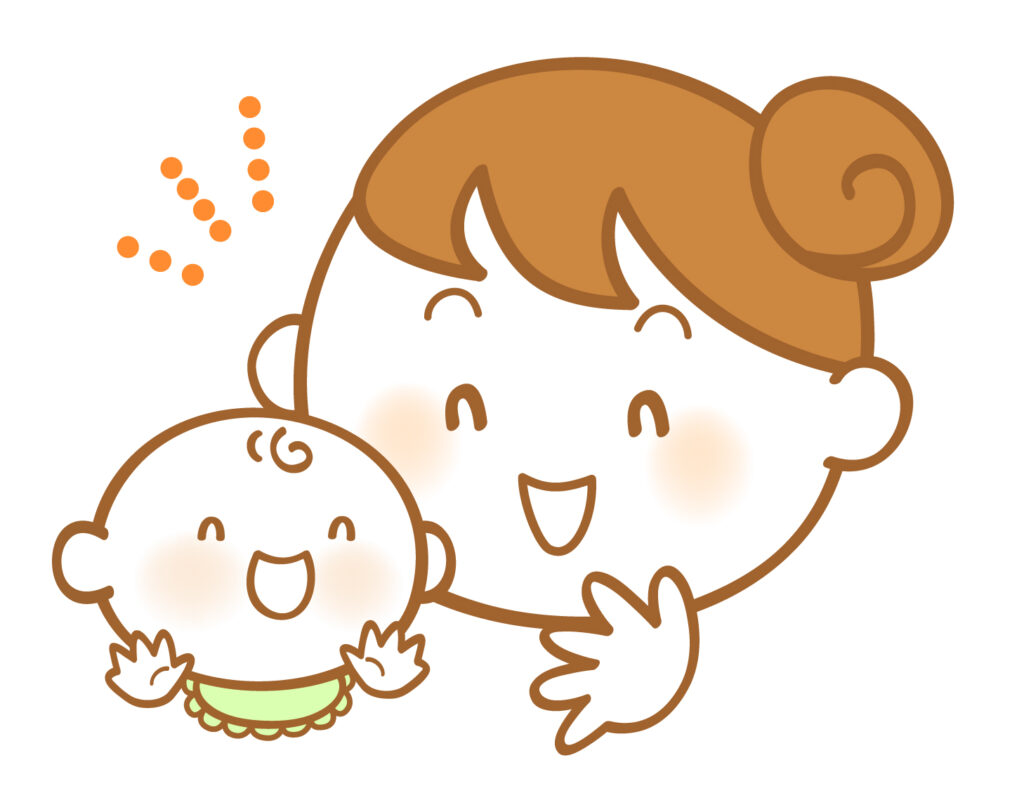
子どもは、親の想像以上に育っていき、自分自身で成長していきます。親はその補助的な役割で構わない。
完璧を求めず、時には間違えたり、予定通りでなくても大丈夫。笑顔が出せない日があってもいい。常識と違っていてもいいし、軸が変わってもいい。うわべだけの付き合いのママ友・パパ友なら、いなくてもいい。
親も子どもも凸凹でいい。自分の強さも弱さも受け入れることができれば、他者にも寛容になれるのです。
参考文献:いい親よりも大切なこと ~子どものために“しなくていいこと”こんなにあった!
今回はこちらの文献を参考にしました。
いい親になりたいと願うことで、自分を苦しめすぎてしまうこともあります。でも、子どものために、『しなくていいこと』を見極めることで、自分自身が楽になる。結果、自分に心と体の余裕が生まれたら、もっと子どもを愛せるようになるはずです。
もっと深く知りたい方は、購入をおススメします。
以上です!!

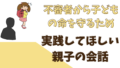
コメント